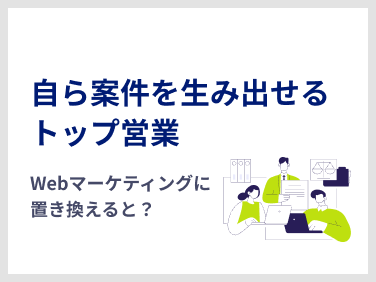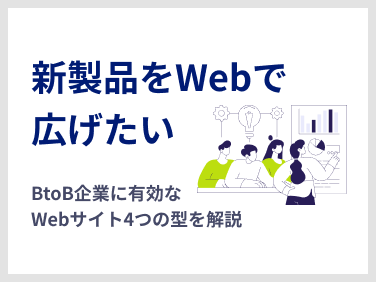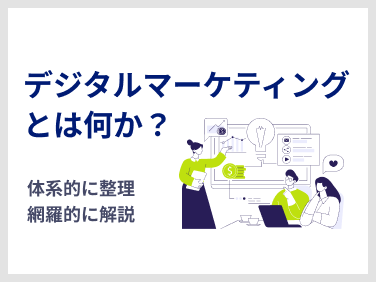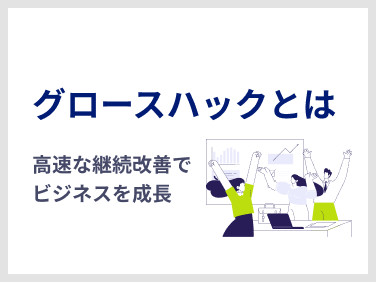なぜ会社は営業パーソンをWebマーケティングの担当にしたがるのか?
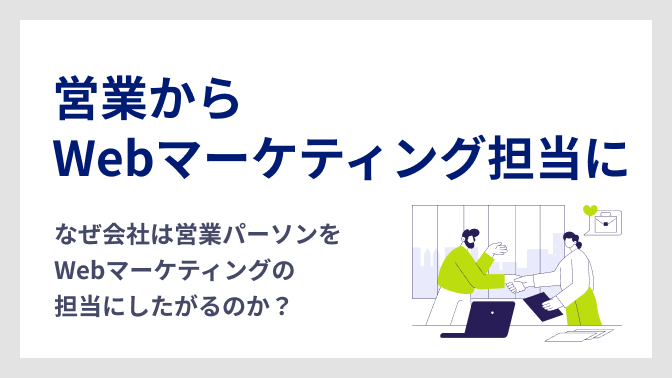
元々営業だった人が、Webマーケティング担当として抜擢されることがよくあります。
ですが「利用者としてWebを日常的に使っていても、仕事となると何が正解で、何をすべきなのかわからない。」という人も多いのではないでしょうか。
会社が営業畑の社員をWebマーケティング担当に任命する場合、いくつかの明確な理由があります。
営業としてのキャリア・培ったものを活かして、会社から与えられた役割を全うし結果を出したい。しかしどこから手を付けて良いかわからない...。
そんなときはなぜ営業パーソンがWeb担当に向いているのか、なぜ会社は営業出身のWeb担当者を育成しようとするのかを考えることが、自分の芯を決めるヒントになります。
1.営業部門との繋ぎ役を担って欲しい
マーケティング部門と営業部門は、それぞれ違った指標に基づいて活動していることがあります。
例えば営業部門は売上・粗利を追求しているので、良質なリード(営業パーソンがアプローチ出来る見込み客リスト)が欲しい。しかし、マーケティング部門では営業部門に渡すリードの「数」を指標にしていたり、数値化できないブランドイメージの管理を担っていたりする等です。マーケティング担当者が考える施策に対して、営業現場が反発することもあります。
営業部門出身のメンバーがマーケティング部門に移籍するのは、異なる部署の橋渡しをする上で適役と判断されるケースがあります。顧客企業の経営者と話をしていると、そのような期待を感じます。
2.営業現場のノウハウをWebに注入したい
実際に顧客と接している営業パーソンの感覚というのは、ときには客観的なデータ・数字よりも重みを持つことがあります。
マーケティングは全社の営業活動のベースとなることもあり、経営上重要なポジションと言えます。リアル営業を経験している人物が担うのであれば「ターゲットに刺さるポイント」の見極めも付けやすいでしょう。
3.優秀な営業パーソンを組織の上に押し上げるステップにしたい
営業センスの良い営業パーソンというのは、会社にとって宝と言えます。しかも、筋道立てて有効な営業アプローチを考える思考力と行動力を伴う人間は、幹部候補として育成対象になるでしょう。
私も過去様々な組織で、優秀なトップ営業パーソンが「部署替え」「配置換え」で会社からの期待を背負い、登っていった人を見てきました。その育成のお手伝いをしたこともあります。
しかし、一方「自分の強みを活かせない」「どうしたら良いかわからない」究極は「これは自分の仕事では無い」等、初期段階で諦めてしまう人が居たのも事実です。
営業からWebへの転換のソフトランディングに、弊社が関与出来ていたらなぁ...と思うこともあったので、営業パーソン出身のWebマーケターが一人でも救われるように願います。
まとめ:営業出身のWeb担当者は高いポテンシャルを持つが、適切なサポートが必要。
営業畑の社員がWeb担当になる場合の良くあるパターンをまとめました。
そのようなケースではスタート時点ではWebの知識はあまり無くても、コンサルティングでご一緒しているうちにめきめき力を付けて行く優秀な方が多い印象があります。
持たされている数字も大きく、上層の期待も厚い。営業出身だからこそ「数字達成」への意識が高く、波に乗れば優秀さを遺憾なく発揮しますが、反面そのプレッシャーに押しつぶされそうになることもあるでしょう。
営業なら自分自身の行動をコントロール出来ましたが、Webでは「自分が動く」だけではどうにもならないことが多く、道に迷うと焦りばかり募ります。
次回は、そんな悩める営業パーソン出身のWebマーケターに、少しでもヒントを提示出来ればと思います。
著者:上田 裕輔(中心設計株式会社 代表取締役社長 / Webコンサルタント)
東証一部上場の専門商社にて営業を経験後、Web系企業を創業。その後再度独立し、大手メーカーのグループ全社/グローバル企業/中堅・中小企業/中央省庁等のWebコンサルティング等に従事。特に産業機械・研究機器をはじめとする専門性の高い領域を中心に18年で500件超のプロジェクトを経験。日本マーケティング学会 会員。
※この記事は事実及び、一定の基準を満たす実務経験に基づき、客観的な視点の元執筆されています。(メディアポリシー)