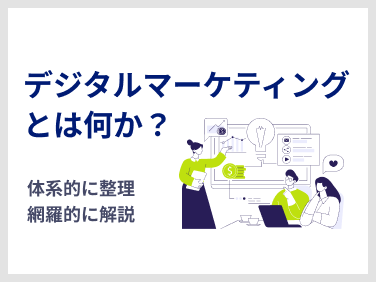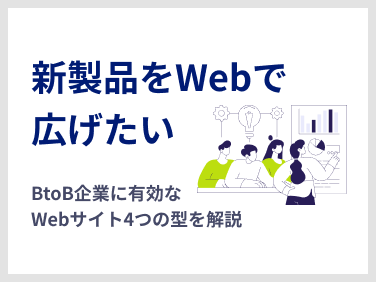グロースハックとは

グロースハック(Growth Hack)とは、限られた予算や人材でも、工夫と実験を繰り返して成果を最大化する成長手法のことです。
直訳すると「成長(グロース)を攻略(ハック)する」──つまり、企業やサービスが急成長するための“戦略的な裏ワザ”とも言えます。
目次
グロースハックとは?意味と定義
まずは「グロースハック」とは何か、その基本的な考え方を押さえましょう。
一般的に「グロースハック」はマーケティングの手法として語られますが、本質は「仮説→実行→検証→改善」の高速なPDCAを小さく繰り返す考え方です。
また近年ではマーケティングだけでなく、営業、開発、カスタマーサポートなど部門横断で取り入れられるようになっています。
グロースハックの歴史
この言葉がどのように生まれ、広がってきたのかを知ることで、背景と目的がより理解しやすくなります。
グロースハックという言葉は、Dropboxの市場拡大で活躍したSean Ellis(ショーン・エリス)によって、2010年頃に提唱されました。
スタートアップ企業が限られた資源の中で急成長を目指すために、従来の広告やプロモーションに頼らず、サービスや機能そのものを使ってユーザーを増やす──そんな発想が出発点でした。
実際、Dropboxでは「友達を紹介するとストレージ容量が増える」という仕組みを通じて爆発的にユーザーを獲得。
このような“プロダクトと成長を結びつける設計”が、グロースハックの原点となりました。
現在では、BtoBビジネスや中堅企業、地方企業でも「少ない投資で、成果を確かめながら改善する」実践的なアプローチとして広がっています。
グロースハックの特徴とメリット
グロースハックの特徴
小さく始める
完璧な計画や大型リニューアルよりも、まずは小規模な施策を行い、その効果を素早く確認します。
たとえば、フォームの一部改善、LPの見出し変更、バナー位置の変更など、小さなテストを重ねて改善サイクルを生み出します。
数値で判断する
主観的な印象や感覚ではなく、ユーザー行動データやCV(コンバージョン)率、滞在時間、直帰率など具体的な指標を元に意思決定を行います。
部門をまたぐ
マーケティングに閉じず、営業部門と連携して営業資料や営業メールを改善したり、開発部門と協力して使いやすさや見た目の工夫(UI/UX)の調整を行ったりするなど、組織を横断して取り組むことが可能です。
グロースハックによる、企業にとってのメリット
予算が少なくても始められる
広告出稿や大型開発を行わず、既存のWebサイトや資料、ツールを活用するだけでも成果が出せます。
成果を可視化でき、社内提案もしやすい
小さな実験によって得られる数値を使って、社内に「何がうまくいったか」を伝えやすくなります。
実験→成功→拡張という流れでリスクを最小化
まずは限定的な対象で効果を検証し、成果が確認できてから他のチャネルやコンテンツに横展開するため、投資の無駄が減ります。
グロースハックとマーケティングの違い
似たように見えるこの2つの考え方ですが、目的や進め方に明確な違いがあります。
| 項目 | マーケティング | グロースハック |
|---|---|---|
| 対象範囲 | 市場分析〜ブランディングまで | ユーザー獲得や改善に集中 |
| 投資額 | 大きくなりがち | 小さく始められる |
| 検証サイクル | 中長期 | 短期・反復 |
グロースハックは「広く・長期で考える」マーケティングと異なり、「まず試す」「数字で見る」ことを重視したアプローチです。
そのため、手元にあるリソースで何かを始めたいと考える中堅企業やWeb担当者にとって、非常に実践的な考え方といえます。
グロースハックが有効な業界例
製造業・メーカー(BtoB)
展示会や代理店頼みの営業が主流だったBtoBメーカーでは、近年Web経由でのリード獲得に注目が集まっています。
例えば、製品カタログをPDFでダウンロードできるようにする、事例紹介ページにCTA(問い合わせボタン)を設置するなどの改善でも、Web経由の商談数が増加するケースがあります。
また、問い合わせ前に製品スペックや導入事例を閲覧する傾向があるため、コンテンツの拡充と行動データの計測によって、営業活動の質も向上します。
商社・卸業
全国に営業拠点を持つ中堅商社では、営業ナレッジの属人化が課題になりがちです。
これに対し、営業担当者のトークスクリプトや成功事例を記事化し、Webやメールマーケティングで発信することで、見込み顧客の教育と信頼構築につなげることが可能です。
また、ヒートマップやクリック率の計測ツールを使って、「どの資料が最も読まれているか」「どの段階で離脱しているか」を分析することで、施策改善のPDCAを素早く回せるようになります。
外資系企業・地方支社
グローバル展開している企業の日本支社や、地方に拠点を持つ企業にとっても、グロースハックは有効です。
本社のガイドラインや意思決定プロセスが厳しい中でも、小規模なWeb施策を“試験的に”導入することで、現地独自の仮説検証が可能になります。
成果が出れば、ローカルイニシアチブとしてグローバルに提案する材料にもなり、デジタル推進の足がかりになります。
IT・SaaS系企業
プロダクトとマーケティングが連携しやすいIT企業では、特にグロースハックとの相性が良いです。
具体的には、UIの一部を変更して継続率を改善したり、オンボーディングメールの文面を変えて初期離脱を防いだりといった施策が実行されています。
また、A/Bテストや行動分析ツールを活用して数値の変化をリアルタイムで把握しやすく、仮説検証のサイクルをスピーディーに回せる環境が整っている点も強みです。
グロースハックの進め方(4ステップ)
実践するうえでの基本的な流れを4つのステップで解説します。
1.課題を定める
「Webサイトからの問合せが少ない」「リードは取れるが受注につながらない」など、現場の数字や感覚に基づいて課題を特定します。
2.仮説を立てる
「フォームの項目が多くて離脱しているのでは?」「LPのファーストビューで訴求力が足りていないのでは?」など、ユーザーの行動や心理に基づいた仮説を立てます。
3.改善施策を実行する
「フォームの入力項目を3つに絞る」「LPのCTAボタンを目立つ位置に変更」「見出しをベネフィット訴求型に変更」など、仮説に対して具体的な打ち手を設計し、迅速に実行します。
4.効果を測定し、次の施策へ
「CV率が20%改善した」→「他ページにも同様の変更を適用」など、成果を数値で確認したうえで展開・最適化を繰り返します。
よくある失敗例とその回避策
グロースハックを始める前に知っておきたい、つまずきがちなポイントとその回避方法をまとめました。
失敗例:成果が出るまで半年かかると思って何もしない
回避策: まずは“3日でできる施策”を見つけることがカギ
完成度よりもスピードを重視し、例えば「フォームの項目数を減らす」「タイトルを変えてみる」など、即日でも試せる改善から始めましょう。
改善した箇所のデータを比較すれば、次の施策へつながる材料になります。
失敗例:とにかくツールを入れて満足する
回避策: ツール導入の前に“目的と仮説”を明確にする
何を改善したいのか(例:離脱率を下げたい、資料DLを増やしたい)を明確にした上で、「そのために何が問題か?」という仮説を立てることが先決です。
ツールはその検証のために使う手段であり、導入が目的になってはいけません。
失敗例:社内の説得から始めようとして頓挫する
回避策: “説得”より“実績”を先に作る
上司や関係者の理解を得る前に、小さく始めて数値で結果を出すのが効果的です。
成果が出た後に報告・共有を行うことで、「この調子で進めてよい」と後押しされやすくなります。
報告にはグラフや比較表などの“見える化”が有効です。
失敗例:一度の失敗でやめてしまう
回避策: 失敗は“データ”と“学び”として活用する
グロースハックにおいて失敗は前提です。
重要なのは、失敗の理由を分析し、次の改善案につなげること。
施策ごとに「仮説→結果→振り返り→次のアクション」という記録を残しておくと、チーム内でのナレッジ共有にも役立ちます。
社内でグロースハックを導入するには?
グロースハックを社内で導入する際にもっとも重要なのは、「まずは小さく成功すること」です。
最初から大きな改革やシステム導入をしようとすると、関係部署の合意形成や稟議、リソースの確保が壁になります。
そこで、まずは自分の業務範囲内で完結できる、小さな改善施策を設計し、短期間で実行してみることが効果的です。
たとえば、既存のWebフォームを改善してCV率(コンバージョン率)を少しでも上げる、営業資料をLP(ランディングページ)に転用して計測できるようにするなど、すぐに着手できる工夫が候補になります。
このような施策は、専用ツールや大きな予算が不要で、IT部門の協力を仰がずに実施できる場合も多く、スピーディーな成果につながりやすいのです。
そして、得られた成果は必ず「見える化」して社内に共有しましょう。
定量的な数値(例:CV率改善、滞在時間、離脱率の変化など)と、改善の背景、仮説、施策の内容を簡潔にまとめることで、上層部や他部門の理解が得やすくなります。
こうした“実績ベース”の共有が重なることで、「まずはやってみる」文化が社内に浸透し、徐々に部門横断での取り組みや、中長期的な改善計画へと発展していくのです。
まとめ|グロースハックは“成果の共通言語”
グロースハックは、少ないリソースでも成果を出しやすい実践的な手法です。試行と改善を重ねることで、小さな成功を生み出し、それを社内の共通言語として展開していくことができます。
特に現場の担当者にとっては、自らの成果を「数字」で示し、社内を前向きに動かす力にもつながります。
まずはできる範囲から一歩を踏み出し、改善を重ねていくことが、組織全体の変化を生む第一歩になるはずです。
執筆者:関根(中心設計株式会社 コンサルティングディレクター)
最先端の研究分野をターゲットにしたマーケット開拓が得意。理系のバックグラウンドを活かし難解な論文や研究資料を読み解く。当社新卒入社。動物が好き。
監修者:上田 裕輔(中心設計株式会社 代表取締役社長 / Webコンサルタント)
東証一部上場の専門商社にて営業を経験後、Web系企業を創業。その後再度独立し、大手メーカーのグループ全社/グローバル企業/中堅・中小企業/中央省庁等のWebコンサルティング等に従事。特に産業機械・研究機器をはじめとする専門性の高い領域を中心に18年で500件超のプロジェクトを経験。日本マーケティング学会 会員。
※この記事は事実及び、一定の基準を満たす実務経験に基づき、客観的な視点の元執筆されています。(メディアポリシー)