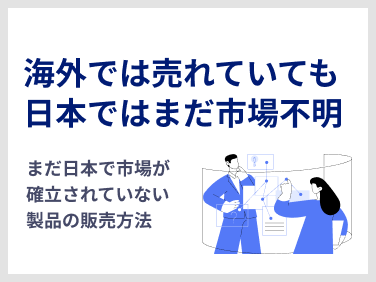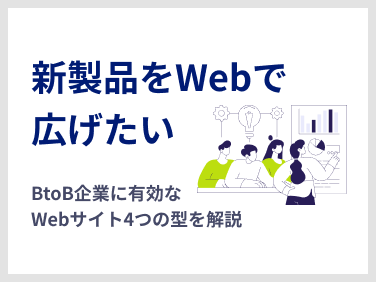展示会営業とWeb営業はどう違う?得意分野を使い分けて相乗効果を狙うには
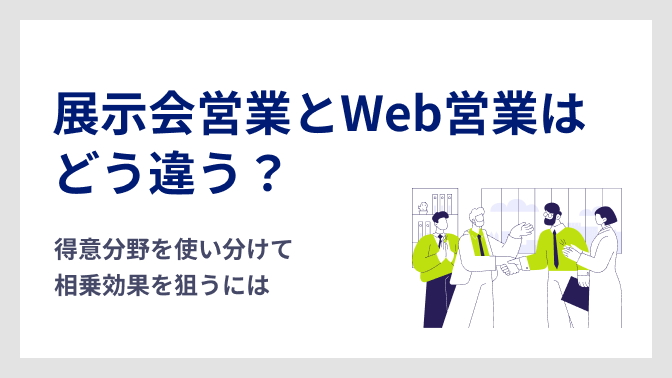
新規開拓の営業手法として展示会営業は、うまくやれば2〜3日の間に多くの見込み客と実際に話ができ、反応も直に感じることができるため、有益なマーケティング手法と言えるでしょう。
展示会営業には、ノベルティの頒布による個人情報・アンケートの取得など、様々な戦略があります。皆様少しでも成果を高めるために、工夫されていることかと思います。
実は、私もWeb業界に来る前は「頻繁に展示会営業をしている会社のBtoBの営業パーソン」でした。(現在はWebマーケティングのコンサルタントをしています。)
営業だった当時は、ビッグサイトや自社主催の展示会でブースに立ったり、大勢のお客様を前にプレゼンセミナーを行ったりしていました。
現在は、Webマーケティングに携わっていますが、Webマーケティングと展示会営業は「新規の認知を得る」という意味で、よく活用される手法であると感じています。
今回は、展示会営業とWebマーケティングの共通点・違いを見ていき、それぞれの良さを生かしたマーケティングについて考えていきます。
目次
展示会営業とWebマーケティングの「共通点」
先ほど「新規の認知を得る」という意味で、よく活用される手法と表現しましたが、双方の共通点として言えるのは次の3つです。
共通点
- 狙ったターゲットがあつまる場所へ露出できる
- 様々な温度感の来訪者が訪れる
- 露出しても、ニーズがある人に来てもらわないと意味がない
順に見ていきましょう。
共通点1. 狙ったターゲットがあつまる場所へ露出できる
展示会の強みは、その分野に対する何らかの興味・感心・ニーズがある人が集まる場であるということです。
例えば本日のビッグサイトにおける展示会の予定を見てみましょう。(2025年7月22日時点)
- TECHNO-FRONTIER 2025
- メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2025
- 第11回 猛暑対策展
- 第12回 労働安全衛生展
- 第4回 騒音・振動対策展
- 第3回 COMNEXT -次世代通信技術&ソリューション展-
- 第2回 SPEXA -【国際】宇宙ビジネス展-
- 産業DX総合展
(タイトルを見ているだけで個人的に行きたくなってしまう内容ですが、今行くと社のメンバーに怒られますので、ぐっとこらえて今記事を書いています。笑)
さて、これが同日同じ場所で開催されている展示会のリストです。
競合他社も出展していますので、その分野にニーズがある来訪者が集まります。
展示会は「特定の分野に感心がある人が集まる場」ですが、Webの場合「業界ポータルサイト」や「検索エンジン」が、これに当たります。
例えば製造業であればイプロスが有名ですね。
検索エンジンが、なぜ「その分野に感心がある人が集まる」かというと、検索エンジンはキーワードごとに個別の市場を形成しているからです。
例えば「真空乾燥器」というキーワードで検索する人たちというのは、真空乾燥器の情報にニーズがある人たちです。
「真空乾燥器」という「特定の分野」に関心を持つ人たちが、検索エンジンに集まり「真空乾燥機」と検索します。
つまり検索エンジンは「ある分野に関心のある人たちを集める場」としても機能しているのです。
共通点2. 様々な温度感の来訪者が訪れる
展示会に訪れる人の「温度感」は様々です。
「本気で選定・検討」している人もいれば、「広く情報収集している段階」の人もいます。あるいは、たまたま横を通ったときに「なんだろうこれ」と思っただけの人もいるでしょう。
Webも同じです。
製品・サービスの申し込み、お問い合わせに関して「複数のWebサイトを見て、既に2〜3社に絞り込んでいて、後はどちらかに声を掛けるだけ」という段階の人もいれば、「とりあえず情報を集めよう」という人もいます。
あるいは、たまたまWebを見ていて「なんだろうこれ」と思っただけの人もサイトに訪れます。
とても似ていますね。
共通点3. 露出してもニーズがある人に来てもらわないと意味がない
展示会では「3万人来場!」のような景気の良い数字の発表がありますが、御社のブースに来て、足を止めて説明を聞いてくれたり、資料を持ち帰ってくれる人は何人くらいでしょうか?
少ないと100人か、ノベルティ配り作戦などで数を稼ぐだけの施策をしていなければ、2~300人いれば良い方ではないでしょうか。
その中で後日アポが取れて商談になる人はどれくらいでしょう?
数人は会ってくれるけど、情報収集の延長レベルで、がっかりすることも多いかもしれません。特にBtoBでは展示会に行くレベルの情報収集段階では、まだ具体化は先だったりと、足が長い印象です。
Webでも同じです。ニーズの無い人をいくら集めても意味がありません。
集客の際は「量」と「質」の2つの面を意識する必要があります。
展示会営業とWebマーケティングの「違い」
ここまで展示会営業とWebマーケティングの共通点を見てきました。
ここからは双方の「違い」を見ていきます。ご紹介するのは次の5項目。
違い
- 展示会はスポット、Webはずっと
- 購買意欲が低い人に会いやすいか
- 時間・場所という制約の有無
- 対応する営業パーソン・説明員の必要性
- 人の力量に依存するか否か
これら「違い」を見ていくことで、展示会営業とWebマーケティング、それぞれの「特性」を明らかにしてみましょう。
違い1. 展示会はスポット、Webはずっと
展示会は開催期間のみ集客効果を持ちます。「スポット」だからこそ集まるパワーを期待します。
対して、Webはサイトが機能していれば「ずっと」集客し続けます。
違い2. 購買意欲が低い人に会いやすいか
展示会の場合、ニーズが顕在化していない人とも話すチャンスが多くあります。
商品/サービスの存在すら知らない人に認知させ、アピールし、受注に繋げる可能性もあるということです。
また、ニーズが無い人に「欲しいと思わない理由」を聞くマーケティング調査もできるでしょう。
Webを使う場合、基本的にニーズが顕在化していない人とは直接会えません。欲しいと思っていない人は、問い合わせしないからです。
その場合はまず顕在化させるためのタッチポイントを作り出し、興味を持たせ必要だと思わせるストーリー展開を行うなど、中長期的な取り組みが必要になります。
即効性を求めると大規模な広告キャンペーンを張る等の方法もありますが「投資」レベルのため、予算が潤沢な会社でなければできません。
違い3. 時間・場所という制約の有無
展示会は会場が開いているのは1日数時間程度で、場所も大都市のコンベンションセンターが中心です。
しかしWebは24時間機能し続け、場所の制約もありません。
違い4. 対応する営業パーソン・説明員の必要性
展示会の隠れたコストとして、設営のための対応工数と、当日ブースに立つ人の工数があります。
この工数は馬鹿になりません。一度積算してみると良いでしょう。
Webでは説明はWebサイトが、こうした機能を果たすため、常時複数人が張り付いている必要はありません。
違い5. 人の力量に依存するか否か
展示会で声掛けが上手かったり、短い時間で顧客の状態に合わせた話の展開ができたり、さらにはその場で訪問アポイントまで取り付けたりすることができる優秀な営業パーソンがいます。
一方で、説明するのにいっぱいいっぱいで、状況に合わせた話をするレベルに達していない説明員もいます(新人の頃の私もそうでした)。
つまり人の力量に依存する面が大きいです。
ですが、Webは常に一定のパフォーマンスを出し続けます。
同じ品質の説明を行い、ニーズによる振り分けを適切に行い、ユーザの知りたいことに合わせて訴求し、受付対応まで行って実案件を生みます。
人の退職や昇進等の再配置でパワーダウンしない、再現性のある集客が可能ということです。
これら展示会とWebの特性の違いから、併用することで相乗効果も見込めます。
例えば展示会で接触した、意欲レベルの浅い相手が、展示会後にWebサイトを見て興味を喚起できたり、実は別の商品/サービスへのニーズがあって、その商談に繋がる可能性もあります。
また、Webで展示会情報を出すことで、展示会自社ブースへの送客ができることもあるでしょう。
展示会営業とWebを併用し、相乗効果を!
これら展示会とWebの特性の違いから、併用することで相乗効果も見込めます。
例えば展示会で接触した、意欲レベルの浅い相手が、展示会後にWebサイトを見て興味を喚起できたり、実は別の商品/サービスへのニーズがあって、その商談に繋がる可能性もあります。
また、Webで展示会情報を出すことで、展示会自社ブースへの送客ができることもあるでしょう。
弊社でも、デジタルマーケティング支援をしていると、お客様からよくこう言われます。
「資料請求や問い合わせがあった人ですが、この人は以前展示会で名刺交換していた既存リードです」と。
それは、既存リードだから価値が無いということではありません。
むしろ「検討段階が進んだタイミングを、Webで改めて捉えることができた」ということを意味します。
営業する側としては、温度感もわからない多数の既存リードの中から、貴重な時間を有効に使い「誰に個別アプローチをするか」を判断できる基準が得られるということが、おわかりいただけるでしょうか?
そのように、既存リードを温めて、営業アプローチを掛けるベストなタイミングを見出すのも、デジタルマーケティングの有用性です。
コロナ禍を経て、世の中はデジタルに大きくシフトしています。
新しいことを少し加えるだけで、様々な可能性が開きます。
これまで展示会営業を活用していた会社がWebに力を入れるとしたら
まずは「自社のビジネスは、Webで集客できる可能性があるか」というところから検討していただくと良いでしょう。
そのために、現状分析から行うことをお勧め致します。
分析は、Web市場の規模算定や、競合他社とのポジショニングの中で、Web市場で戦えるか、伸びる余地があるのかということが主眼に置かれます。
もし具体的に何から始めたらいいのかわからないという場合は、弊社にご相談いただくことも可能です。
まずはご相談を
弊社では担当者様や予算に合わせた柔軟な対応が可能です。
例えば、組織上層部を動かすために体裁の整ったレポートが必要という場合でも、弊社では比較的少額で対応しています。
ご相談頂く方が代表者様や事業責任者様など、決定権を持つ方であり、提出物の体裁を気にしない場合は、ご相談頂ければ無料相談の範囲で「いける/いけない」の根拠を数字や過去の経験知を元にお話することもできます。
展示会営業からWeb営業に転換したいお客様は、是非一度、無料相談をお申し込みください。
著者:上田 裕輔(中心設計株式会社 代表取締役社長 / Webコンサルタント)
東証一部上場の専門商社にて営業を経験後、Web系企業を創業。その後再度独立し、大手メーカーのグループ全社/グローバル企業/中堅・中小企業/中央省庁等のWebコンサルティング等に従事。特に産業機械・研究機器をはじめとする専門性の高い領域を中心に18年で500件超のプロジェクトを経験。日本マーケティング学会 会員。
※この記事は事実及び、一定の基準を満たす実務経験に基づき、客観的な視点の元執筆されています。(メディアポリシー)